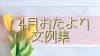目次
保育園での節分の出し物にはどんなものがある?

お正月が過ぎればもうすぐ節分がやってきます。
節分といえば定番は豆まきですが、それ以外にはどのような出し物があるのでしょうか?どんな企画をしよう、、?と悩んでいる保育士さんも多いのではないでしょうか?
そこで今回は、園児たちも楽しめる節分の出し物についてリサーチしてみました!製作編、ゲーム編、それ以外と種類ごとにまとめています。
節分の由来についても最後に解説してあるので、導入として、園児たちの年齢に応じて簡単に説明してあげると、より節分を楽しめますね!
【保育園の節分】流れ・進め方

保育園で節分のイベント・遊びをしよう!
でも具体的に何をすればいいの?
とお考えの保育士さんもいらっしゃるのではないでしょうか。
保育園の節分イベントをする際の具体的な流れの例はこんな感じです。
- 「節分」の由来や意味を子どもたちに伝える
- 子どもたちと、節分にちなんだ製作をして、飾ってみる
- 先生が鬼役となり、豆まきをしてみる
- クイズや手遊びなどの遊びをする
まず、節分とはなんなのか、なんで鬼や豆が関係しているのかということを子供たちに共有することで、子どもたちの教養、興味関心が向上します。
これは保育園で節分をするねらいでもあります。節分の由来については本ページの後半でご紹介しています。参考にしてみて下さい。
その後は、簡単にできる製作物に挑戦してみましょう。
楽しみながら工夫して作ることは成長にもつながります。また装飾をすることでイベントの雰囲気を作ることもできますね。
そして、歌やゲームで遊びましょう!節分にちなんだゲームはたくさんあります!
【保育園の節分】出し物①製作編
1.鬼のお面
節分といえば鬼のお面は必須です!
園児たちがそれぞれ作った個性豊かな鬼のお面を被って遊んで、節分を盛り上げましょう!
装飾として、壁に飾ってみるのもいいですね。
・画用紙
・はさみ
・のり
・輪ゴム
・毛糸やモールなど(飾り付け用)
2.鬼の装飾
今度は、壁面装飾などにもなるような鬼の飾りをご紹介します。
折り紙だけで手軽にできるので、子どもたちと一緒にトライしてみましょう!
・赤や青の折り紙
おまけ:折り紙でこん棒も作ってみよう!
3.升(豆入れ)
節分といえば豆まき!
そのために使う豆入れを手作りしてみるのもよいのではないでしょうか?
牛乳パックを使えば簡単に作ることができます!牛乳パックをはさみで切って、周りに画用紙を切って貼り、自由に絵を描けば完成です。
また、牛乳パック以外にも、折り紙だけでより簡単に作る方法もあります♪
・牛乳パック(画用紙、折り紙でもOK!)
・はさみ
【保育園の節分】出し物②ゲーム編
1.鬼的あて

このゲームはみなさんもおなじみだと思います。
鬼のお面を被った先生が走り回って、園児たちが鬼に向かって豆をまく、というのが定番ですね。
中には鬼の仮装をした先生を怖がる園児もいるかもしれません。
その場合には、鬼の顔の的を作って、みんなで的をめがけて豆を投げる、という遊び方もおすすめです。
この時鬼の口を穴のようにしてみんなで穴に豆やボールを投げ入れる、というゲームをしてみるのも面白いと思います。
2.鬼の出てくる昔話をもとにして劇
鬼に関連して、鬼の出てくる昔話や絵本を題材にして劇をしてみるのはどうでしょうか?
おすすめとしては「桃太郎」、「一寸法師」などは有名かつ鬼を退治するお話なので、劇をすることによって、豆まきにもより一層熱が入るかもしれませんね。
昔話でなくても、絵本や紙芝居を事前に読み聞かせてあげて、それを題材にして劇をしてみるのもいいかもしれません。
桃太郎 -ももたろう(日本語版)アニメ日本の昔ばなし
いっすんぼうし – 一寸法師(日本語版)
3.節分ボーリング~鬼を倒せ!~
このゲームは、まず、ペットボトルの上に鬼の顔を貼り付けて、鬼に見立てます。トイレットペーパーの芯に画用紙を貼って鬼に見立てても〇
そしてそれをボウリングのように並べて、丸めた新聞紙やゴムボールなどを転がして倒して遊びます。新聞紙に茶色や黄色の画用紙を巻いて豆に似せると、より雰囲気が出ますね。
豆まきの時のように散らかることがなく、片付けがいらないのでとてもおすすめです!
4.節分輪投げ~鬼のツノめがけて!~

このゲームは、大きな鬼の顔を作って、そこに画用紙やトイレットペーパーの芯などを使ってツノをつけてあげます。そしてそのツノに向かって輪を投げます。
ツノの形を変えてみたり、様々な鬼を作ってみたり、幼児に合わせて難易度を変えて作ってみるのがおすすめです!
5.節分クイズ
節分にちなんだ知識をクイズ形式で出題!
クイズ形式にすれば、園児たちもより楽しく節分について知ることができますし、準備も場所もいらないのでちょっとした空き時間や待ち時間に行うことができるのでおすすめです。
クイズをすることで、由来や風習を楽しく学べそうですね!
【保育園の節分】出し物③その他(ペープサート、手遊び、絵本)
1.ペープサート
ペープサートは保育園などで園児たちにわかりやすく行事の由来を教えるのに適しているのでよく使われる出し物です。
登場キャラクターを動かしたり、ジェスチャーを大きくして感情を込めたりできるので、絵本や紙芝居とは違って、臨場感が増し、飽きさせることなく園児たちを楽しませることができるので、おすすめです。
節分豆まき(ペープサート)
2.手遊び「鬼のパンツ」
鬼の仮装をしたら、みんなで童謡の「鬼のパンツ」を歌ってみましょう!振り付けもつけて踊れば、きっと盛り上がること間違いなしです!
♪おにのぱんつ
3.手遊び「豆まき」
うたに合わせて豆まきの手遊びをしてみるのはいかがでしょうか?振り付けも単純でわかりやすいのでどの年齢の園児たちでもきっと楽しめると思います。
♪豆まきの歌
4.絵本
次は、おすすめの節分にまつわる絵本を紹介します。
語彙力を発達させ、想像力を豊かにするのにとっておきな読み聞かせ!
どちらの本も対象年齢が2.3歳~となっているため、どの年齢の園児でも節分の由来や内容がわかりやすいように書かれています。
【保育園の節分】おまけ 節分の由来
皆さんは「節分」という言葉の意味をご存じですか?
「節分」という言葉には、季節を分けるという意味があります。つまり、季節の分け目を指すので「立春、立夏、立秋、立冬」と一年に4回あります。
その中でも立春は、旧暦では年の変わり目である大晦日にあたる大事な節目であったこと。また、暖かい春の訪れとして一番人々に待ち望まれていたため最も重要視されるようになりました。
そのため、立春だけを節分と呼ぶようになりました
『なぜ豆まきをするの?』
節分に豆まきをする理由は中国の文化が深く関係しています。
豆まきは中国の「追儺(ついな)」という行事に由来しています。追儺とは、別名「鬼やらい」とも呼ばれます。
中国では季節の変わり目には邪気(鬼)、魔物が生じると考えられていました。その邪気を追い払うために魔滅(まめ)に通ずる豆で邪気を追い払い、無病息災を祈りました。
これが日本に平安時代に宮中行事として取り入れられるようになったのが豆まきの始まりです。また日本では穀物には邪気を祓うパワーがあると信じられていたため、日本の文化として取り入れやすかったとも考えられています。
『ワタナベさんは豆をまかなくていい?』
この話は、平安時代の「大江山の鬼退治」が基になっています。当時、大江山に住み着いて人々を苦しめていた鬼の棟梁「酒吞童子」を成敗すべく、武士である源頼朝は部下を従えて向かいます。
この時、目覚ましい活躍をしたのが「頼光四天王」の一人とされる渡辺綱。以来、鬼はこの「ワタナベさん」を恐れるあまり、豆をまかれなくても鬼、自ら「ワタナベさん」から逃げるようになったと言われています。ちなみに、同じく四天王の一人で金太郎のモデルとして知られる坂田金時にも同様の言い伝えがあるので、サカタさんのお家でも節分の際には福を招くだけで良いのだそうです。「ワタナベさん」と「サカタさん」はラッキーですね!
『なぜ節分には恵方巻きを食べるの?』

恵方巻きはかつて「丸かぶり寿司」や「太巻き寿司」と呼ばれ江戸時代から明治時代にかけて大阪の花街で芸子や商人たちが芸遊びをしながら、商売繁栄を祈って食べていたのがはじまりといわれています。
その後、1989年に大手コンビニチェーン店であるセブンイレブンの野田靜眞氏が「大阪には節分に太巻き寿司を食べる風習がある」と知ったことをきっかけに、太巻きを「恵方巻き」と名付け、売り出しました。それから恵方巻きは一気に全国に広がり、様々な場所で販売されるようになりました。
恵方巻きは七福神にちなんで七種の具材で作られ、それを一気に丸かじりすることで商売繁栄の運を一気にいただくという意味が込められているとされています。
また、その年の恵方(神様がいる方角)を向いて食べます。食べている間にしゃべってしまうとご利益が逃げてしまうと考えられているため、黙って食べるのがルールとされています。
おわりに
いかがでしたでしょうか?今回は保育園で使えるおすすめの節分にまつわる出し物を紹介してみました。節分は古くから歴史のある行事です。季節や伝統を感じながら製作や遊びを楽しめたらいいですね…!一年に一回の節分、園児たちとぜひ思い出に残るイベントにしましょう!
また公式Instagramにおいても、保育のノウハウやあるあるを沢山紹介しています。気軽に楽しめるコンテンツばかりですので、ぜひチェックしてください!

よくある質問
保育士くらぶにはどんな記事がありますか?
保育士くらぶには現役の保育士・幼稚園教諭や保育士を目指す学生さんにとって手遊びや保育内容など今日から役立つ保育のネタをご紹介しています。こちらのトップページより色々な記事をお楽しみください。
保育士くらぶの最新の記事はどこから見られますか?
最新の記事はこちらの保育士くらぶトップページよりご覧ください。月間12本~15本の記事をアップしています。保育で使える季節の遊びや歌、連絡帳の書き方などもご紹介しています。
保育士くらぶのオリジナル動画はどこから見られますか?
保育士くらぶのオリジナル動画はこちらの保育士くらぶyoutubeチャンネルでまとめて見ることが出来ます。保育士くらぶyoutubeチャンネルでは保育で使える歌や遊び、制作以外にも転職のコツや求人の探し方も解説しています。