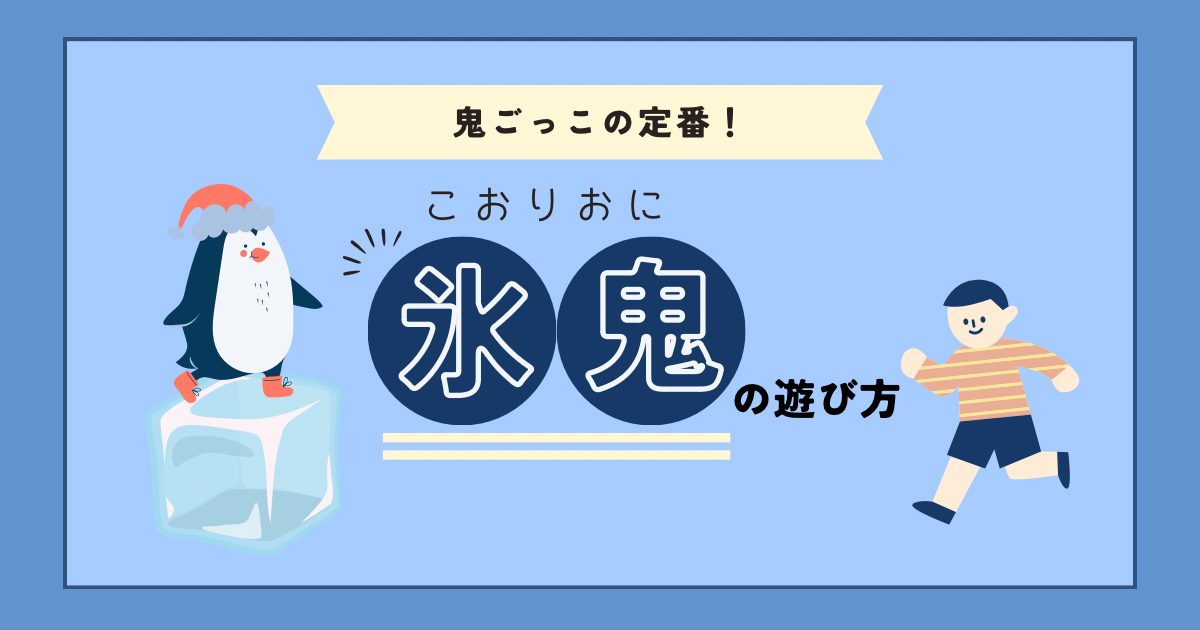定番の遊びである鬼ごっこ。室内、室外に関わらず遊べるため、保育の現場でも遊ぶ機会が多いことと思われます。今回は、そんな鬼ごっこのアレンジである氷鬼についてまとめました。子供達が鬼ごっこに飽きてきた、鬼ごっことは違うかけっこ遊びをさせてやりたいと思っている保育士さん必見。氷鬼の基本の遊び方から、基本のルールがまとめてあります。また、氷鬼をする際の指導案に役立つねらいや、氷鬼を行う上で保育士さんがやるべきこと。さらには、氷鬼を楽しむポイントや、氷鬼のさらなるアレンジ方法と、氷鬼について余すところなく知ることが出来ますよ。ぜひ参考にしてみてくださいね。
氷鬼とは【基本の遊び方】
鬼ごっこをアレンジしたもの

ではまずはじめに氷鬼の基本の遊び方についてみていきましょう。氷鬼は鬼ごっこをアレンジしたものです。鬼ごっこに飽きてきたり、他のかけっこ遊びがしたくなった時におすすめですよ。
遊び方
①最初に鬼をだれにするか決めます。
②逃げても良い範囲をみんなで確認します。
③鬼になった人は数を10数えて、数え終えたら逃げている人達を追いかけていきます。
④タッチされた人はその場で凍り動けなくなります。
⑤凍った人は他の人にタッチしてもらうことで再び動けるようになります。
⑥鬼が多くの人を凍らせることができたら鬼の勝ちです。
氷鬼について【基本のルール】
タッチするときは優しくすること

次に氷鬼をするにあたっての基本のルールをみんなで押さえておくことが大切です。基本のルールの1つ目として、タッチするときは優しくするということを確認しておきましょう。氷鬼に一生懸命になりすぎると、追いかけたり逃げたりする際にかなりのスピードがでます。そのスピードのままに逃げている子をタッチしようとすると、強く叩いてしまいかねませんよね。強く叩くと前に向かって転倒することもあり、ケガの原因になるでしょう。そのため、氷鬼で遊ぶ前に優しくタッチすることを子供達に意識させることが必要なのです。意識することで、遊ぶ時にケガをするリスクを減らすことが出来ますよ。
同じ子ばかりを狙わないこと
基本のルール2つ目としては、同じ子ばかりを狙わないということを確認しておきましょう。クラスで氷鬼をはじめ、さまざまな鬼ごっこをする時がありますよね。すると、クラスの中でも仲の良い子をねらいがちになったり、捕まえやすい子ばかりを狙ったりといった状況がでてくることがあります。そのため、氷鬼で遊ぶ前にはいろんな子を追いかけるように、クラスのみんなで確認することが大切です。同じ子ばかりを狙うと、追いかけられる子がとても疲れてしまい氷鬼を楽しめなくなることが考えられます。また、逆に追いかけられない子が退屈してしまい全員で楽しめなくなるということも。均等に追いかけることが難しくても、同じ子ばかりを狙わないよう子供達に意識を向けてもらうと良いでしょう。
タッチされたら動かないこと
基本のルール3つ目としては、タッチされたら動かないということを確認しておきましょう。タッチされたにも関わらず動いてしまう子がいると氷鬼が成り立ちませんよね。ルールが分からずに動いてしまう子、タッチされたことを認めたくなくて動いてしまう子、理由はさまざま。しかし、動いてしまう子がいると捕まえても捕まえても意味がなく、鬼になっている子が疲れ果ててしまいます。保育士さんが見張っているとはいえ、一部始終を見張ることは困難ですよね。そのため、しっかりとみんなでルールを確認し、ルールを守って遊ぶことを子供達に意識させましょう。
氷鬼をするねらい
多くの友達とルールを守って楽しく遊ぶことを学ぶ

では次に氷鬼をするねらいについてみていきましょう。1つ目のねらいは、多くの友達とルールを守って楽しく遊ぶことを学ぶということです。氷鬼は複数人の子供で遊ぶあそびですよね。そのため、多くの友達とひとつのことを行い楽しむことを学ぶことが出来ます。同じルールのもとで取り組むため、社会性や協調性を育むことに繋がりそうですね。氷鬼で遊ぶ前には、子供達みんなでしっかりとルールを確認すると、スムーズに遊びに入れるでしょう。そんなルール知らなかったということがないようにしたいですね。
身体を動かす喜びを感じ身体的発達を促進させる

2つ目のねらいは、身体を動かす喜びを感じ、身体的発達を促進させるということです。氷鬼をするということは、鬼の人は逃げている子を追いかけますし、鬼ではない子は走って逃げますよね。つまり、体全身を使うことのできる遊びなのです。遊びながら身体を動かせるので、子供達は身体を動かす喜びを感じることでしょう。そして、たくさん遊びたくさん動くことで、身体的発達を自ずと促進することが出来ます。氷鬼をすることで、こうした子供達にとってのメリットを享受することができるのです。
氷鬼を楽しむためのポイント
鬼を適宜交代させる

次に、氷鬼を楽しむためのポイントをみていきましょう。まず1つ目は、鬼を適宜交代させるようにしましょう。同じ子供がずっと鬼の役割をしていると、体力をとても使います。また、ずっと同じ役割をしていると退屈してしまう原因になることも。時間を決めてぐるぐると役割を回せると良いですね。鬼を決める時もできるだけ公平に決めることができると、子供達の不満も最小限に抑えられそうです。鬼をするのが嫌な子供がいる場合、鬼に対してかっこいいなどのポジティブな印象を与えると効果的ですよ。
鬼が誰なのか分かりやすいように目印をつける
2つ目は、鬼が誰なのか分かりやすいように目印をつけると良いでしょう。氷鬼に夢中になっていると誰が誰だか分からなくなる時があります。この人は仲間なのか、それとも鬼なのか判断することができないと、逃げるべきなのかわからず逃げ遅れることも。そうなると、氷鬼を楽しみきることができませんよね。鬼が誰なのか分かりやすくすることで、子供達は鬼を認知しやすく、逃げる・追いかけるの判断がつきやすくなります。格段に遊びやすくなりますし、子供達も氷鬼を楽しみきることが出来るでしょう。
人数が多い場合は鬼を増やす
3つ目は、人数が多い場合は鬼を増やすということです。氷鬼で遊ぶ人数にもよりますが、だいたい5~6人に対して1人の鬼くらいが妥当でしょう。大変そうな場合は、保育士さんが鬼になるという手もありますね。保育士さんが鬼になる場合は、実際に遊びながら子供達と再度ルールを確認できるというメリットがあります。氷鬼で遊んだことがないクラスで行う際におすすめですね。人数が多くなると、それだけ追いかけなければならない人数が多くなります。鬼になった子供の負担が大きくなりすぎないよう注意して、工夫するようにしましょう。
子供達へ逃げられる範囲を事前に伝えておく
4つ目は、子供達へ逃げることのできる範囲を事前に伝えておくようにしてください。範囲を決めていないと、子供達はあらゆるところに逃げ隠れしてしまいます。遊びに夢中になり、危険なところに入ってしまう可能性も。また、あまりにも範囲を広くすると、保育士さんの目が届かずケガをしてしまう危険性もあります。そのため、遊ぶ前にはしっかりと逃げられる範囲を決めて、確認しましょう。範囲が決められることで、より盛り上がりますよ。
氷鬼のアレンジ
バナナ鬼
次に氷鬼をアレンジした遊びとしてバナナ鬼を紹介します。バナナ鬼とは、鬼にタッチされたらバナナになってしまう鬼ごっこです。氷鬼の基本的なルールを理解できるようになった4・5歳児に特に人気の高いかけっこ遊びと言えるでしょう。バナナを他の果物に変えたり、皮をむく動作をアレンジも楽しめますよ。 【遊び方】①最初に鬼をだれにするか決めます。②逃げても良い範囲をみんなで確認します。③鬼になった人は数を10数えて、数え終えたら逃げている人達を追いかけていきます。④タッチされた人は両手を挙げて手のひらを頭の上で合わせ、バナナの真似をします。⑤バナナになった人は、まだタッチされていない人に皮をむいてもらうことで、再び逃げることができます。⑥鬼が多くの人をバナナにすることができたら鬼の勝ちです。
氷鬼を行う上で保育士さんがやるべきこと
危険物やケガのもとになる物が落ちていないか確認する

では、最後に氷鬼を行う上で保育士さんがやるべきことを確認していきましょう。1つ目は危険物やケガのもとになる物が落ちていないか確認することです。室内室外問わず遊べる氷鬼。道具も要らず気軽に遊べるため、急に氷鬼をしようとなることも。そんな時、下におもちゃや、なにかの破片が落ちていたらどうでしょうか。走っている途中に誤って踏んでしまい、ケガをしてしまうということが考えられるでしょう。どんな遊びをする時も、子供達が安全に遊ぶことのできる環境を保育士さんが作ることが大切ですが、走り回る遊びの時は特に重要になってきます。ケガのもとになりそうな物は、遊ぶ前にきちんと取り除くようにしましょう。
子供達同士が衝突しないよう見守る
2つ目は、子供達同士が衝突しないよう保育士さんがしっかりと見守ることです。追いかけることや逃げることに夢中になると周りが見えなくなることがあります。そうすると、子供達同士がぶつかってしまうことも考えられるでしょう。走っているのでそれなりにスピードがでている状態。そんな状態でぶつかるとケガの原因になりますよね。そのため、保育士さんがしっかりと子供達を観察し、危ないなとと感じた時は間に入るなどして対応してくださいね。
逃げられる範囲を守っているか確認する
3つ目は逃げられる範囲を守っているか確認しましょう。保育士さんの目が届くように範囲を決めておくことの大切さを、前の章でお伝えしたと思います。しかし、子供達の中には遊びに夢中になりすぎて範囲外にでてしまう子がいるかもしれません。そんな時は、「ここからはでたらだめだよ~」と優しく注意すると良いでしょう。ルールを何度も認識することで、子供達も氷鬼で遊ぶことに慣れてきます。しかし、慣れる前は思いもよらない行動をとる子供もいるかもしれないため、保育士さんはしっかりと見守るようにしてくださいね。
まとめ
ルールをしっかり守って氷鬼を楽しもう!

いかがでしたでしょうか。氷鬼で遊ぶことで、鬼ごっことは違う楽しさを感じることができます。また、ルールを理解して考えながら遊ぶため、頭を使いながら遊ぶことのできる遊びと言えるでしょう。さらには、社会性や協調性を育み、みんなで楽しむこともでき、子供達のより良い発達にとても効果的な遊びでもあります。今回紹介した基本のルールやポイントをおさえつつ、子供達が夢中で楽しめる環境・空間を保育士さんが作ってあげて下さいね。これから暖かくなり、室外で遊ぶことも多くなると思います。ルールをしっかり守って氷鬼を楽しみましょう!
よくある質問
保育士くらぶにはどんな記事がありますか?
保育士くらぶには現役の保育士・幼稚園教諭や保育士を目指す学生さんにとって手遊びや保育内容など今日から役立つ保育のネタをご紹介しています。こちらのトップページより色々な記事をお楽しみください。
保育士くらぶの最新の記事はどこから見られますか?
最新の記事はこちらの保育士くらぶトップページよりご覧ください。月間12本~15本の記事をアップしています。保育で使える季節の遊びや歌、連絡帳の書き方などもご紹介しています。
保育士くらぶのオリジナル動画はどこから見られますか?
保育士くらぶのオリジナル動画はこちらの保育士くらぶyoutubeチャンネルでまとめて見ることが出来ます。保育士くらぶyoutubeチャンネルでは保育で使える歌や遊び、制作以外にも転職のコツや求人の探し方も解説しています。